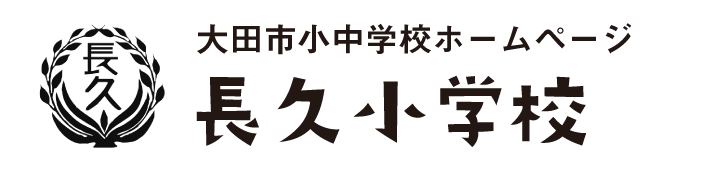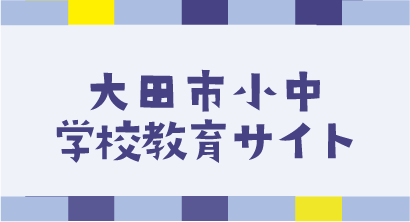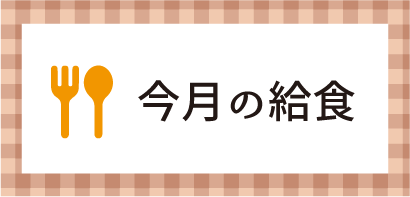校長室より(令和6年11月)
■自分の思いや考えを自分らしく表現できる子に■ 校長 和田 正利
15日の学習発表日には、たくさんの皆様におこしいただきました。子どもたちの発表を参観していただきありがとうございました。どの子も張り切って一生懸命取り組んでいる姿にとてもうれしく思いました。
学習して分かったことやそこから自分で考えたことなどを分かりやすく伝えることに、この学習発表の意味があると思っています。相手に分かりやすく伝えるためには、どのような人に伝えるのか、どのような内容を伝えるのか、どのような順番で伝えるのか、どのような手段や方法を用いると伝わりやすいのかなど考えることがたくさんあります。今の子どもたちは、変化が激しく予測が難しい時代を生きていくことになります。そんな時に必要な力が、「答えが一つに定まらない問題に自ら解を見出していく思考力・判断力・表現力等の能力」「主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度」「十分な知識・技能」です。
本校では、子どもたちにこのような力が身に付くように日々の学習活動を展開しています。今回の学習発表の経験を生かして、子どもたち同士が豊かに関わり合いながら、主体的、対話的により深く学んでいく。そして、そのような活動を通して、失敗を恐れず友達の力を借りながら進んでチャレンジしていくことができるようになってほしいと願っています。
22日には、中国五県造形教育研究大会が大田一中、大田小、長久小、久屋小で開催されます。この4校は、この大会に向けて令和
4年度から3年間研究に取り組み、当日は3年生と6年生の図画工作の授業を公開します。
本校では、研究主題を「つくる喜び みる楽しみ かかわる つながる 造形教育」とし、確かな願いをもった子どもの学習活動を生み出すために研究を続けてきました。図画工作の授業を通して子どもたちに身につけさせたい力を、
〇発想力・構想力
〇自分で試行錯誤する力
〇のびのびとした表現力
〇学び合う力
の4つとしました。このような力をつけるために、授業においては題材、活動の場、授業展開などを工夫したり、認める、見守る、価値づける、掘り下げる、提案する等の効果的な働きかけを工夫したりしています。どのようにしていけば長久小学校の子どもたちの力を伸ばしていけるのか、私たちも試行錯誤しながらよりよい授業をめざして子どもたちと学習しています。
ここに掲げた4つの力は図画工作だけに当てはまるというわけではありません。どの教科の学習においても必要となる力だと思います。「こうなりたい」「こんなふうにしてみたい」「こう工夫すればできそうだ」「こんことを伝えたい」等、確かな願いをもって、その願いをかなえるために試行錯誤しながら根気強く取り組み、自分らしい表現ができる子どもに育ってほしいと願っています。
22日は、研究会のため1,2,4,5年は臨時休業となりますが、午前中は学校で勉強している3,6年と気持ちを一つにして家庭で勉強してほしいと思います。